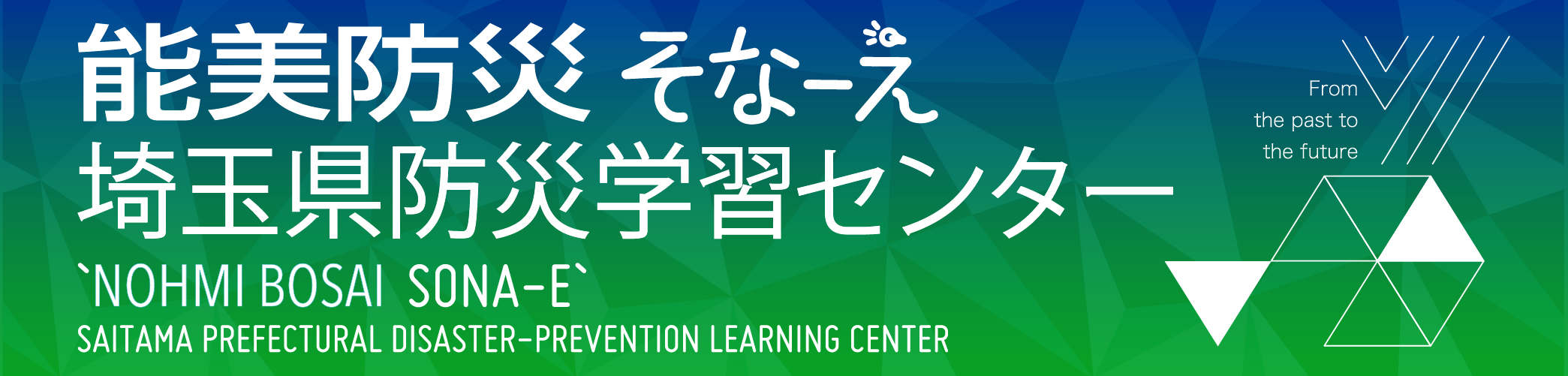防災Q&A
●防災に関するQ&A
Q:大きな地震が発生したら、どうすればいいですか?
A:【学校や家にいる時】 机やテーブルの下に入り、しっかりと頭を守り、落ちてきそうな物から身を守りましょう。また、揺れがおさまったら、コンロの火は消しましょう。
【屋外にいる時】 ブロック塀や電信柱、自動販売機など、倒れてくるかもしれないものから離れましょう。カバンや上着などで頭を守りながら、公園や空き地などの安全な場所に避難しましょう。
【山や海にいる時】 山の近くでは、すぐに崖からはなれ、海の近くでは、なるべく高い場所や建物に避難しましょう。
【エレベーターの中にいる時】 全部の階のボタンを押して、止まった階で降りましょう。エレベーターは地震になると緊急停止しますが、パニックにならずインターホンで連絡しましょう。
Q:その次は、何に注意すればよいでしょうか?
A:揺れがおさまったら、火の元の確認や情報収集をします。ガス漏れの有無を確認し、ラジオやインターネットから正確な情報を入手しましょう。家屋倒壊の恐れがあれば、電気のブレーカーを落とし、近くの公園など安全な場所へ避難するようにしましょう。
Q:日頃から家庭で心がけることはありますか?
A:寝室やリビングなどは、家具の転倒防止やガラスの飛散防止など、怪我をしないように予防対策をしましょう。
また、避難するための非常用持ち出し袋を準備しておきましょう。
埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/bousaitaisaku/kagunokotei.html
Q:非常用持ち出し袋を準備するポイントは何ですか?
A:最低でも、人数×3日分(できれば1週間分)の水や食料、薬などを用意しておきましょう。
重い荷物では歩きにくいので、水など重たい物は、物置や車のトランク、玄関先など、なるべく分散して置きましょう。
更に軽くするために、缶詰食料の代わりに、比較的軽い乾燥食品なども検討しましょう。
家族で各自1つのリュックを用意し、取り出しやすい場所に保管しましょう。
Q:なぜ、3日分の備えが必要なのでしょうか?
A:災害発災直後は、公的な支援物資が届くまで数日かかると言われています。それまでの間、最低3日分の水と食料を備え、自分の力や地域の方々と協力して乗り越えられるようにするためです。
Q:どのような物を備蓄すればいいですか?
A:一例を紹介します。
水:ひとり1日、3リットル程度
食料:缶詰、レトルト食品など(自分や家族の食べたいもの)
照明:懐中電灯、ランタンなど(日頃から電池等も確認しておきましょう)
燃料:卓上カセットコンロ・カセットボンベなど(キャンプ用品でも代用できます)
簡易トイレ、ラジオ、現金(小銭)、保険証など (災害で怪我をした際に使用する可能性があります)
また、個別の事情により必要となる物も用意しておいた方が安心です。
・眼鏡や老眼鏡、普段から服用している薬、アレルギー食、生理用品など
・小さなお子様がいらっしゃる場合:おむつ、粉ミルク、おしりふきなど
・ペットがいる場合:ゲージ、リード、ペットフードなど
・その他、携帯電話の充電器、ウエットティッシュなど
Q:備蓄品を準備したが、つい点検を忘れてしまいます。何かいい方法はありますか。
A:ご自身やご家族などの特別な日を防災の日と決めて、年に数回点検するといいかもしれません。※ローリングストックという方法で水や食料の賞味期限のチェックも忘れずにしましょう。
※ローリングストックとは
日頃から保存食を備蓄しておくことも大切ですが、日常の中に食料備蓄を取り込むという考え方もあります。普段から少し多めに食材、加工品を買っておき、使ったら使った分だけ新しく買い足していくことで、常に一定量の食料を家に備蓄しておく方法をローリングストックといいます。
ローリングストックのポイントは、特別なものを用意するのではなく、日常的に使う保存性のよい食料品を少し多めに『買い置き』し、その備蓄(ストック)した食料品を、定期的に食べて、食べた分を買い足すことで、備蓄品の鮮度を保ち、いざという時にも日常生活に近い食生活を送ることができます。
埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/bousaitaisaku/3day-bitiku.html
◆避難について
Q:避難する場所がわかりません。どこに避難すればいいですか?
A:各自治体のハザードマップを参考に指定された避難所へ避難するようにしてください。
日頃から家族でどこに避難するか話し合っておくことも大切です。
Q:避難する時のポイントは何ですか?
A:避難する前に、もう一度火元を確認しガスの元栓を閉め、電気のブレーカーも落とします。
荷物は最小限の非常持出品に限りリュックサックに入れ、両手が使えるよう背負って避難しましょう。
外出中の家族には避難先を記した連絡メモを残しましょう。
移動する時は、履きなれた靴で、塀や自動販売機のそば、狭い道、川べり、ガラスや看板の多い場所は避けましょう。日頃から、危険な箇所が無いか点検しておくことも大切です。
Q:避難所へペットも連れて行っても大丈夫ですか?
A:事前に各自治体に確認していただくと、万が一の時スムーズに避難ができると思います。
出来る限り、ゲージなどに入れて頂くことを推奨します。
また、居住空間についても、各自治体で対応が違うので事前に確認しておきましょう。
Q:災害時に家族や友人と連絡を取る方法を教えてください。
A:災害時は一般の電話がつながりにくくなります。
・家族や友人の安否確認などには、NTTの災害用伝言ダイヤルサービス「171」を活用しましょう
・また、携帯電話会社各社の災害時に安否情報を登録・確認できる「災害用伝言サービス」もあります。登録が必要な場合がありますので、各携帯電話会社に確認してください。
・この他にも、被災地になっていない遠方の親戚などに安否情報を知らせしておき、その親戚などに電話すれば安否情報がわかる「三角連絡法」があります。事前に家族で話し合い、親戚などにお願いしておくことが必要です。
・公衆電話は災害時に接続制御を受けない優先電話なので、携帯電話を含めた一般電話よりもつながりやすくなっています。また、被災地で広域停電が発生した場合には緊急措置として無料で開放されます。
Q:災害用伝言ダイヤル「171」の使用方法を教えてください。
A:NTTは、震度6以上の地震発生時など被災地への安否確認電話が集中する場合に「災害用伝言ダイヤル」サービスを開始します。事前契約などは不要で、サービス開始はテレビやラジオで告知されます。171番へダイヤルするとガイダンスが流れるので、それに従って利用できます。
【伝言を吹き込む】 171 → 1 → (市外局番からの電話番号※)→ 伝言を入れる(30秒以内)
【伝言を聞く】 171 → 2 → (市外局番からの電話番号※)→ 伝言を聞く
※被災地の人は自宅や携帯電話などの電話番号、被災地以外の人は被災地の人の番号(市外局番から)
埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/bousaitaisaku/saigaiyoudengon.html